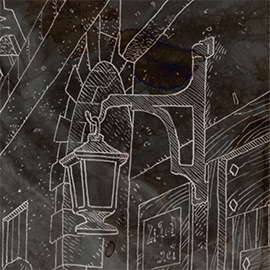
北に聳えるキネッラ山、その麓にひっそりと佇む小さな町は、母なる山の名を冠した「キネレスアルケ」。
太陽が地平の向こうに沈むと、古い家々に透明な灯が燈り、影絵のような住民たちが通りに繰り出します。
こぼれそうなほど果物が並ぶ市場。
賑やかな音楽にあふれる広場。
井戸端で挨拶を交わす大人たち。
入り組んだ路地を駆けていく子供たち。
日々の糧を分け合い、
山がもたらす恵みに感謝する、
変わらない一夜(いちにち)が始まります。
坂田みどり、
作詞:真名辺あや/
キネッラ山より谷を挟んだ南方に小さな街がある。
小さいながらも豊かで活気に満ちた街は、古くからキネッラ山を女神とみなし、街にもたらされる実りや富は女神の恩恵によるもの、という考えが強く根付いている。
この辺り一帯は地質学的にも興味深い点が多く、しばらく滞在して調査したいと申し出たところ、快く同意を得ることができた。
この手記は調査記録とは別に、個人的な記録や覚書のために残すものである。
-12頁
~フィールドワークによる3つの小品(第1曲)
現地調査の初日、街の顔役の案内で各所を見学させてもらった後、ささやかながら私の歓迎会が催された。
ここまでの歓待を受けるとは思っていなかったため、多少気恥ずかしさもあったが、朗らかで親しみやすい住民達の人柄にすぐに慣れることができた。
歓迎会の中で歌われた歌は、老若男女問わず街の誰もが知る歌で、キネレスアルケの住民は物心着く前から聞いて育つという。
「この歌を歌えるようになったら、あなたも立派な街の住民だ」と酒屋の主人が囃し立てたので、私まで一緒に歌わされる羽目になった。
-46頁
思えば私には故郷と呼べるものが無い。
両親の仕事の都合で幼少の頃から各地を転々とし、故に土地への愛着といったものが極めて薄く、生地ですら碌に案内も出来ない有様である。
だからこそだろうか、キネッラ山の噴火の予兆を伝えた時、何の躊躇も無く受け入れた彼らの考えに理解を示すことが出来なかった。
しかし彼らからしてみれば、この街を離れて別の土地で暮らすことの方が余程理解を超えたものだったのだと、今なら分かる気がする。
それは愛街心とでも呼べるものなのか、古くから山と共に生きてきた彼らの文化が培った思想なのか。
いずれにしろ、彼らが堅実に積み上げた日々の暮らしと歴史は、結局余所者に過ぎない私の言葉ひとつでは到底覆せるものではなかったのだ。
-161頁
~フィールドワークによる3つの小品(第2曲)
キネレスアルケの街の名物ともいえる広場の大時計は、60年ほど前に当地の職人達によって作られた。
素朴な雰囲気の街の中にありながら、精巧な仕掛けと繊細な装飾を施された時計は、意外な取り合わせのようにも思われるが、当時の職人達が外国の技術も取り入れながら街の一大事業として製作にあたった結果だという。
毎時鐘の音と共に動き出すからくり仕掛けは、時計と共に街が末長く穏やかな時を刻むことを願い、古くから歌い継がれる子守唄を表現している、と人好きのする街の顔役が教えてくれた。
この美しい大時計は、街のシンボルとして住民達から愛され続けている。
-27頁
その日の深夜1時37分、キネッラ山の噴火が観測された。
発生した火砕流は南方に進出し、キネレスアルケの方角へ向かった。
溶岩塊を含んだ本体は谷に入り込み街を直撃することはなかったが、火山灰とガスを含む高温の熱雲が街を覆い、深夜であったことも相まって逃れられた者はいないと思われた。
夜が明け、私がたどり着いた頃には、辺り一帯は灰で覆われ、焼き尽くされた後だった。
以来、キネレスアルケは今日まで廃墟が残るのみとなっている。
-129頁
女神よ。
彼らが敬い愛した貴女に慈悲があるならば、せめて彼らに魂の安寧を。
-94頁
~フィールドワークによる3つの小品(第3曲)
先日、珍しく夢を見た。
キネレスアルケの近隣の町でまことしやかに囁かれる噂を耳にしたからだろうか。
夜中に廃墟に明かりが灯るだの、鐘の音が聞こえるだの、面白おかしく騒ぎ立てているだけの下らない噂だが、私の記憶を呼び起こすには十分だったらしい。
慎ましく親切な人たち。広場や市の賑わい。古い石畳の感触。
どれも驚くほどに鮮明に思い出された。
長らく足が遠のいていたが、もう一度訪れる気になったのは、そういう訳である。
-145頁
キネッラ山の噴火から数年が経ち、灰に覆われていた土地にも緑が戻り始めていた。
この地を訪れるのも久しぶりだが、あちらこちらに蒲公英が咲き誇る様など、まるで悲劇などなかったかのように思える。
しかし未だキネレスアルケは朽ちるままに任せられ、復興が進む気配はないようだった。
いつか素朴で美しい街並みが、再び戻る日が来るのだろうか。
-173頁
キネレスアルケを見下ろす小高い丘の上で、蒲公英を摘む少女に出会った。
訪れる者も少ないこの土地で、どこから来たのかと問うと、彼女は眼下の廃墟を指差した。
しかし、まさかそんなはずはない。
仮に幸運にもあの災害を生き延びたのだとしても、幼い少女が独りで何年も暮らせる環境ではなかったはずだ。
おそらく何かの間違いか、あるいは私を揶揄っているのだと思われたが、子供を独り残して去るわけにもいかず、ひとまず他の町まで連れて行くことにした。
しかし、私はその時確かに聞いたのだ。
去りゆく少女を見送るように丘の下から響く、あの懐かしい鐘の音を。
-188頁
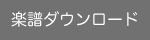
『キネレスアルケの長い永い一夜 -the colors of wonders-』は、以下の販売業者さまにて委託頒布しております。
≫外部リンクKodomore Records